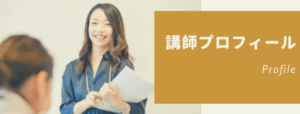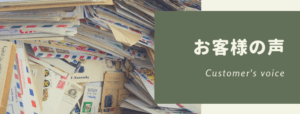離職防止には?関係性を築く傾聴力で勝負!

新しい職場創りを円滑にするために
今すぐ役立つ3つの方法 シリーズ第2弾
こんにちは!人財育成コミュニケーションの西田こずゑです。ご訪問ありがとうございます。

私 西田について詳しくはこちらから
コロナウイルスの影響を受けても変わらぬ新年度が始まりました。
研修等は中止やらオンラインやら工夫がされているようですが、実際の職場は動きを止めません。
今回はせっかくの機会なので、誰もが安心できる職場創りの最初の一歩をお伝えしていきますね。
この投稿から、新入社員、転入社員が5月病を乗り越え、6月の倦怠感を乗り切れるチームがいっぱいできることを願っています。
では、スタート!!
円滑な職場運営のために今のこの時期やっておきたいこと!シリーズ第2弾
目次
コミュニケーションの中で信頼関係を築くのに一番必要なスキルは傾聴力です。

これはこのHPをご訪問してくださる方はご存知だと思います。
では、傾聴力ってどんな力なのでしょうか。こう尋ねると
「簡単!人の話を聞くだけだから、それは得意です。自分は職場でよく聞いてますよ」と言われる上司や先輩の方いっぱいいます。
「話すことはとても難しい、ネタもないし、、上手く伝えられない」というお話は出るのと同じくらい「聞くことは得意ですよ」という方は多いのです。
そんなあなたに今回はいくつか質問いたしますね。
自分の部下やら後輩に対しての聞き方を振り返ってみましょう。

聞き方チェックシートです。
□部下の話を自分の考えと違うと、「おいおい」と途中で遮って自分の理論を通しがちである
□話を聞いている時につい聞き洩らして、そのままにしておくことがある
□相づちは、あまり考えずに適当に打っている
□部下の話を聞いていて、言いたい事がわかると先回りして「あーわかった。こういうことだよね。」と結論を急ぐ
□何が要点かわからなくて「で、つまり言いたい事は何?」と間に挟む
□話の要領を得ないとつい気持ちがイラっとすることがある
□何か別の作業をしながら、部下の話を聞いていることが多い
□部下が困っているだろうと思い、聞いている途中で助言をし始めて、課題を解決してあげた自分はいい上司だと感じる
実はまだいろいろありますが、この辺りにしておきますね。
あなたはチェックがいくつ入りますか。

お分かりかと思いますが、一つでもチェックが入ったら人の話を十分聞けているとは言えないのです。
なかなか手ごわいと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
私もこれができなくて後輩指導や学校現場の子どもの指導で大失敗をいっぱいしてきました。
いきなり全部できるようにとは言えないので新入、転入社員が安心できる職場環境を創るために、すぐできることをお約束通りお伝えしますね。
まずは以下の3つのことを意識してみましょう。

1「で?だから?それで?」は禁句
部下の話は要領を得ないこともあるという前提で話を聞くようにしてみてください。その際、上記のような「で?だから?それで?」という聞き返しはちょっと避けましょう。実はこの言葉、意識せずに使うことが多々ある人もいますが、こう聞き返されると自分が否定されていると感じてしまうものです。
使っている本人は気づかなくても、言い返されると、とても自信をなくす言葉です。
代わりに使うといいのが、「そうなんですね」とか「なるほど」のような言葉。「で?」と、どうしても口走ってしまうなら、「で、君はどう思いますか。」「どうしたらいいと感じますか。」のように質問文を入れてみてください。
2 最後までじっと聞く
要領を得ない前提で聞くことを先ほどもお伝えしましたが、部下や後輩が結論を伝えずに時系列に話をしたり、時折話がそれたりしても、まずはじっと聞きましょう。その時に大切なのが、顔つきをイラっとしたものにしないように。あくまで穏やかな表情を心がけられたら上出来です。
3 適度な相づちやオウム返しで聞いていることがわかるように
子育てと同じで自分に関心を持ってもらえていると思う子どもはどんどん話をしていきます。
その原理でいくと相手にわかるように聞いているよ、というサインを送ると安心できることになります。
ずっと同じ相づちで抑揚もなく聞いている人を見かけますが、相づちは「この人大丈夫かな」という不安感を拭い去るサインなのです。だから、話に合わせて、相づちの種類を変化させる。さらに言えば声のトーンまで変えられるとなるともっと聞いてもらえていると思うものです。
誰でもできる上の3つを実践してみるだけで、あなたへの信頼度はアップ!
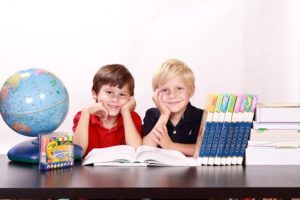
いきなり聞き方のゴールを目指そうとしてもまずはハードルが高いと思うので最初に上の3つだけ心がけてみてください。それだけで、新しく入った新入社員、転入社員はこの上司なら安心だと思えると思いますよ。
ではまた次の機会に、さらにレベルを上げて、職場を円滑にするコミュニケーションの聴き方のコツをお伝えしますね。